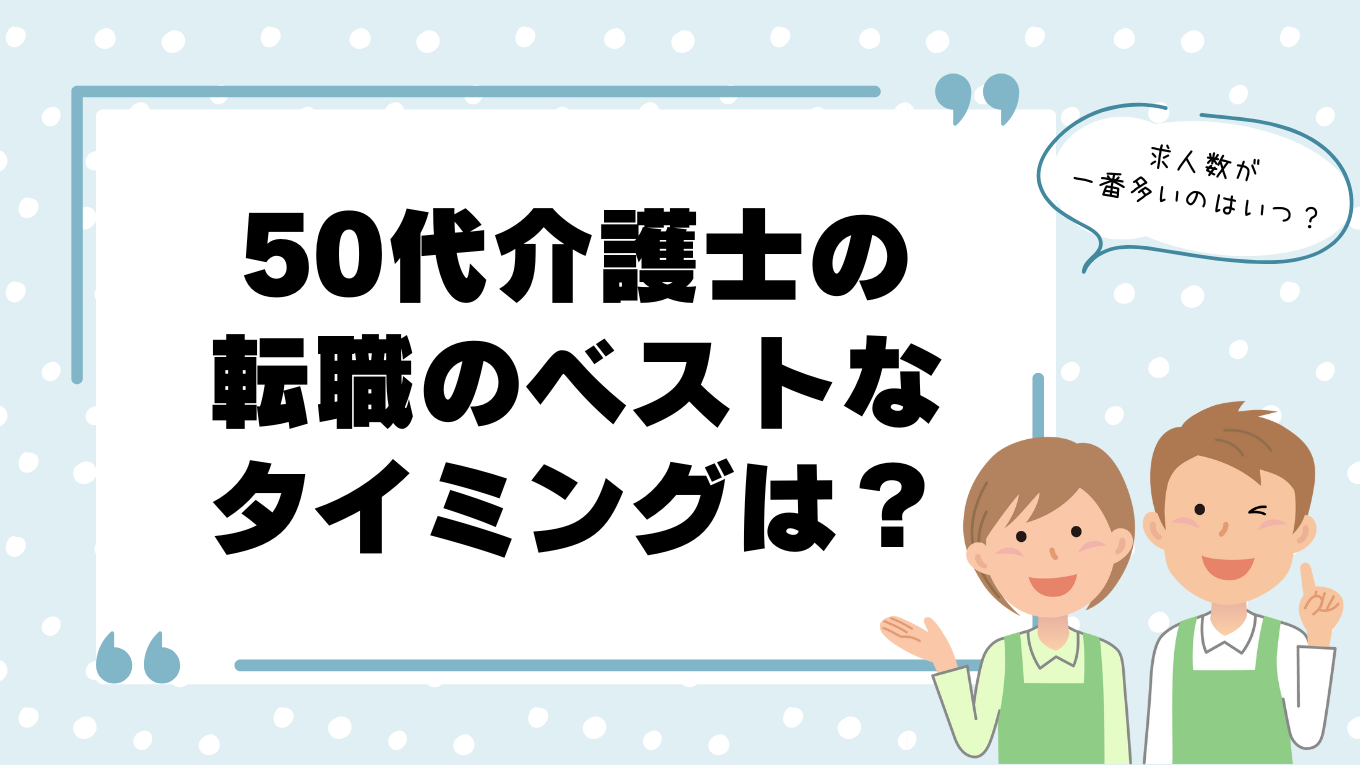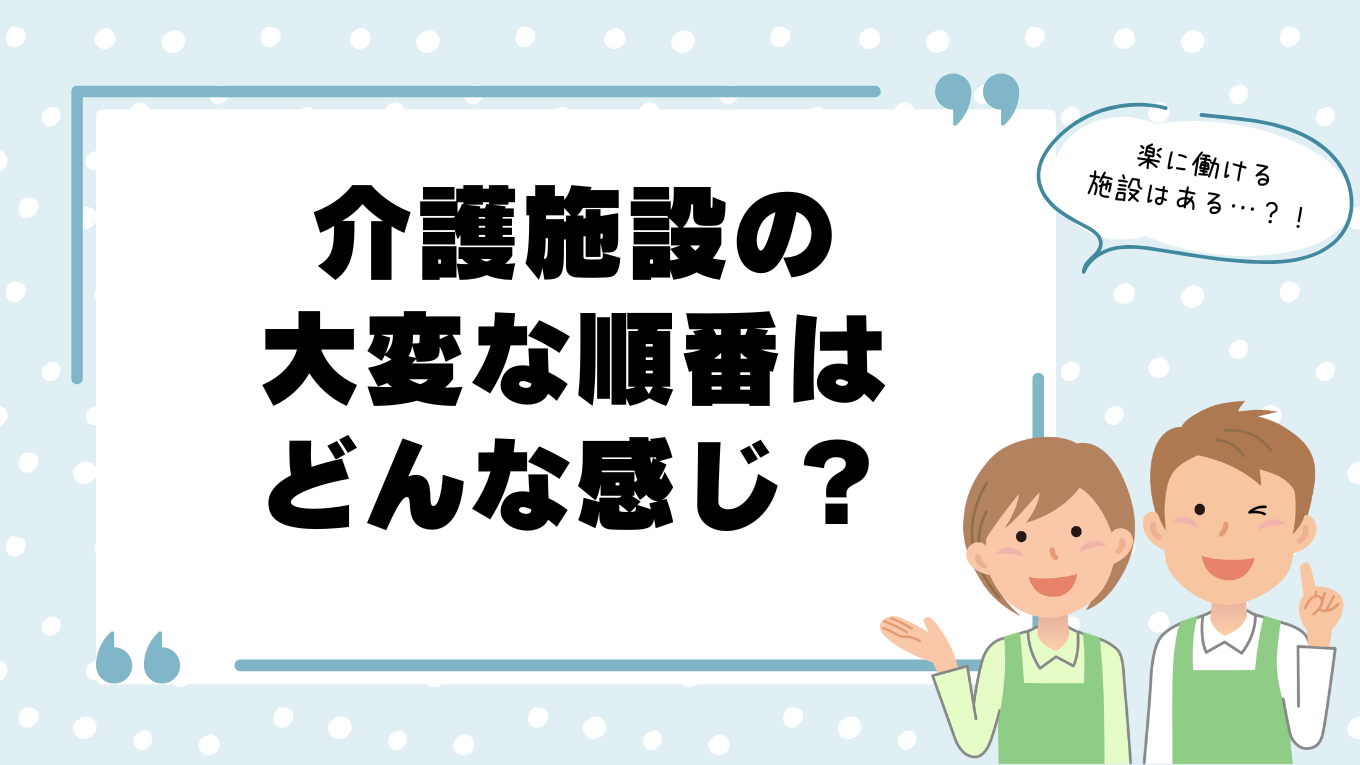60歳を過ぎた介護職の夜勤は体に悪い?避けるべき3つのリスク
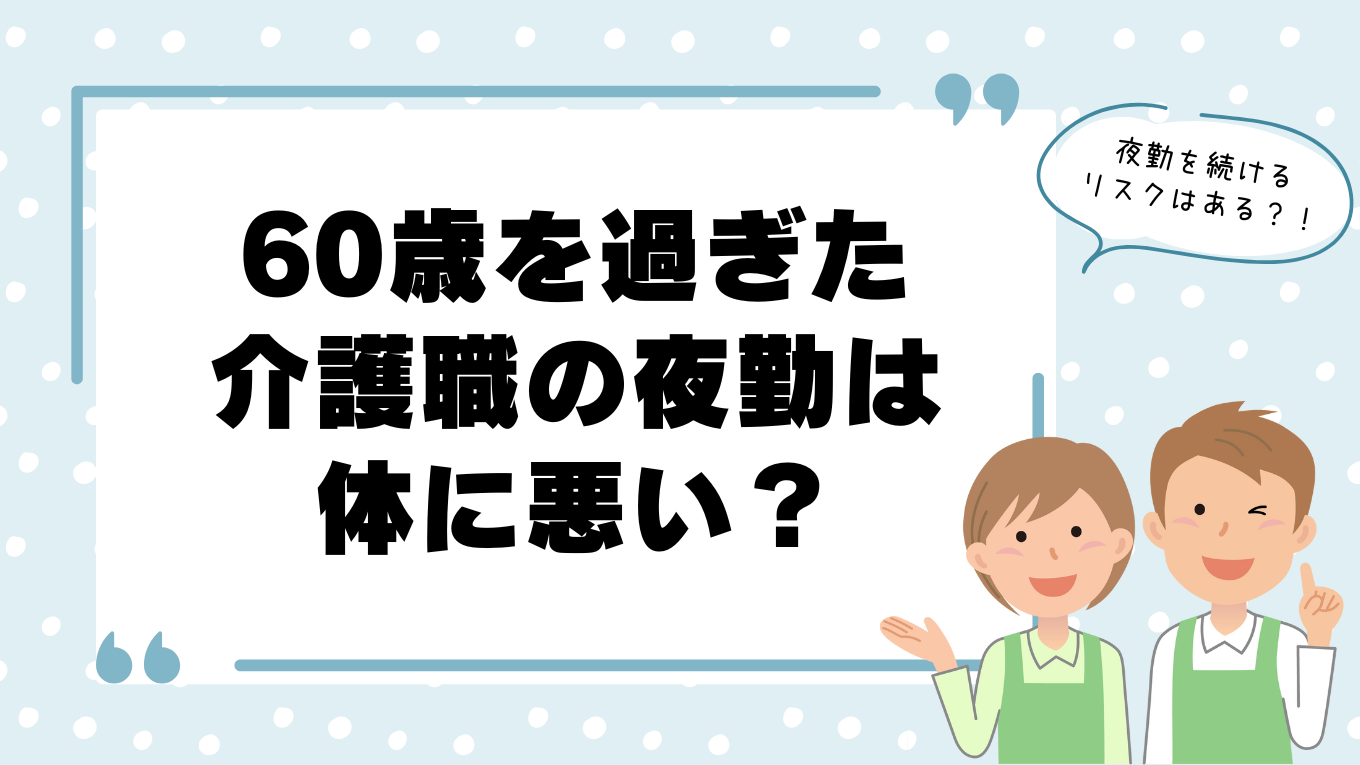
- 60歳を過ぎた介護職の夜勤は体に悪い?
- 無理せず働ける夜勤の目安を知りたい
- 病気が悪化しない働き方はある?
年齢や体力の不安から、夜勤を続けるか迷う人は多いはずです。
夜勤は負担が増えやすい一方で、主な3つのリスクを知れば判断しやすくなります。
この記事では、体への影響と避けるべき3つのリスク、減らす工夫、続けるか見直す基準をわかりやすく解説します。

夜勤を続けるか迷ったら、まず自分の体調や働き方を冷静に見つめ直してみてくださいね!
\転職したい介護士におすすめ/
人気の転職サイトTOP3
 | \介護職口コミNo.1/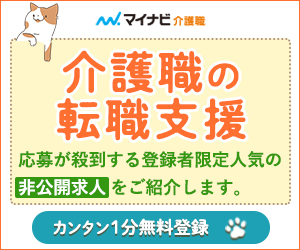 |
 | \残業なし求人多数/ |
 | \無資格・未経験OK/ |
60歳を過ぎた夜勤の体への影響を知る
60歳を過ぎると、夜勤による体への影響が大きくなります。
若い頃と同じように働けると思っていても、体の回復力や睡眠の質は年齢とともに変わっていきます。

まずは「夜勤がどのように体に負担をかけるのか」を知ることが、長く働くための第一歩です。
夜勤が体のリズムを乱す仕組み
夜勤が体にこたえる大きな理由は、「体内時計(生活リズム)」が乱れることです。
人間の体は、朝起きて夜に眠るリズムで動くようにできています。
このリズムに反して夜中に働くと、脳や内臓が「夜なのに動いている」と混乱し、ホルモンや体温のバランスが崩れます。
例えば、夜勤をすると次のような変化が起きます。
- 睡眠の質が下がり、深い眠りが減る
- 食欲や消化のリズムが乱れて胃もたれしやすくなる
- 体温調整がうまくいかず、疲れが取れにくくなる
このように体のリズムが崩れることで、だるさや集中力の低下が続きやすくなります。
年を重ねると回復に時間がかかる理由
若い頃は夜勤明けに少し寝れば回復できても、60歳を過ぎるとそうはいきません。
これは「深い眠り(ノンレム睡眠)」の時間が短くなるためです。
深い眠りは体を修復する時間ですが、加齢とともに減ってしまうため、疲労が残りやすくなります。
また、ホルモンの分泌量も年齢とともに減ります。
たとえば「成長ホルモン」や「メラトニン(睡眠ホルモン)」が減ると、睡眠の質や回復力が低下し、夜勤明けに寝てもスッキリしない状態が続きます。
結果として、
- 翌日の眠気が強く残る
- 日中にウトウトして集中できない
- 食事のリズムが乱れ、食欲がわかない
といった不調が積み重なりやすくなります。
体に負担が出やすい人の特徴
同じ年齢でも、夜勤の影響を強く受ける人とそうでない人がいます。
体に負担が出やすい人には、いくつかの共通点があります。
特に、慢性的な睡眠不足や生活リズムの乱れが続く人は注意が必要です。
体に小さなサイン(頭痛・動悸・めまい・食欲不振など)が出た時点で、夜勤のシフトや働き方を見直すサインと考えるのが安全です。
体への影響を理解しておくと、「まだ頑張れるか」「少し休むべきか」の判断がしやすくなります。
まずは無理をしない前提で、自分の体と向き合うことが大切です。
60代介護士が夜勤を避けるべき3つのリスク

夜勤を続けるうえで知っておきたいのは、無理を重ねるとどんなリスクがあるのかという点です。
夜勤は生活リズムが乱れやすく、体調不良やミスの原因にもなります。
特に60歳を過ぎると、体力や免疫力が低下するため、リスクが高まりやすい傾向があります。
ここでは、夜勤を続ける際に注意すべき3つの代表的なリスクを見ていきましょう。
1.睡眠不足と注意力低下による事故
まず最も多いのが、睡眠不足による注意力の低下です。
夜勤では昼間に眠ることが多く、周囲の明るさや生活音によって深く眠れないことが原因になります。
眠りが浅いまま勤務を続けると、反応速度が落ち、介助中のヒヤリ・ハットにつながることもあります。
また、睡眠不足が続くと次のような症状が現れます。
特に深夜帯の「午前2〜4時」は集中力が最も下がる時間帯です。
その時間帯にトイレ介助や巡回を行う際は、意識して動作をゆっくりにするなどの工夫が必要です。
2.高血圧や糖尿病の悪化
2つ目は、生活リズムの乱れが持病の悪化につながることです。
夜勤では食事時間が一定でなく、血糖値や血圧が安定しにくくなります。
また、夜間は副交感神経が働きにくいため、体が「常に緊張している状態」になり、
血圧が下がりにくくなることもあります。
特に注意したいのは次のような変化です。
こうした習慣が積み重なると、動脈硬化や糖尿病の悪化リスクが上がります。
持病を持つ人は、夜勤シフトの頻度を減らしたり、日勤中心の働き方を検討するのも一つの選択肢です。
3.腰やひざの痛みが長く続く
3つ目は、体の痛みです。
介護現場では、利用者の移乗介助や体位変換など、腰やひざに負担がかかる動作が多くあります。
夜勤では人員が少ないため、同じ姿勢での作業や無理な持ち上げが増えやすく、慢性的な腰痛や関節痛につながります。
特に次のようなケースでは注意が必要です。
痛みを放置すると、筋肉がこわばり、動きが悪くなる悪循環に陥ります。
湿布や痛み止めでごまかすよりも、勤務後に軽く体を伸ばす習慣をつけるほうが長期的に効果的です。
夜勤のリスクを理解しておくと、無理をせず健康を守りながら働く判断がしやすくなります。
次の章では、こうしたリスクを減らすための具体的な工夫を紹介します。
体調不良のリスクを減らす3つの対策

夜勤を完全に避けられない場合でも、工夫次第で体への負担を大きく減らすことができます。
夜勤が続くと、どうしても睡眠不足や体の不調が出やすくなります。
しかし、生活の整え方を少し変えるだけで、疲労やストレスを軽くすることが可能です。
ここでは、すぐに実践できる3つの基本的な対策を紹介します。
睡眠時間と仮眠時間を先に確保する
夜勤で最も重要なのは「眠る時間を先に決める」ことです。
シフトの前後に予定を詰め込みすぎると、睡眠が削られてしまいます。
60歳を過ぎた人ほど、1回の睡眠でしっかり回復することが難しいため、「まとまった睡眠」と「短い仮眠」を組み合わせて休む方法が効果的です。
例えば、次のようなスケジュールを意識するとよいでしょう。
| タイミング | 睡眠・仮眠の目安 |
| 夜勤前 | 2〜3時間の仮眠 |
| 夜勤中 | 15〜30分の休憩仮眠(交代制で) |
| 夜勤後 | 5〜6時間のまとまった睡眠 |
また、睡眠の質を上げるために、
- カーテンで光を遮る
- スマホを寝る直前に見ない
- 部屋を静かに保つ
といった工夫も効果的です。
眠れない日が続く場合は、無理に寝ようとせず「横になって目を閉じる」だけでも回復につながります。
食事と水分とカフェインの整え方
夜勤中の食事や水分補給も、体調を左右します。
特に夜中は消化機能が落ちているため、脂っこい食事を避け、軽めの内容を意識することが大切です。
おすすめの食事例は次の通りです。
また、コーヒーやエナジードリンクなどのカフェインは、摂りすぎると睡眠を妨げます。
夜勤開始の2〜3時間以内に、控えめに飲むくらいがちょうどよいでしょう。
水分はこまめにとり、脱水を防ぐことで体調が安定します。
動き方を見直し同僚と負担を分ける
介護現場では、ひとりで無理をしないことも大切です。
特に夜勤は少人数で動くため、役割をうまく分けることが体への負担軽減につながります。
「自分がやったほうが早い」と抱え込まず、チームで助け合う意識を持ちましょう。
これらの3つの対策を意識することで、夜勤の負担を最小限にしながら働き続けることが可能です。
次の章では、「夜勤を続けるか、それとも見直すべきか」を判断するための基準を整理します。
夜勤を続けるかやめるかの判断基準

夜勤を続けるか迷う時は、感覚ではなく数値や記録をもとに判断することが重要です。
夜勤を無理に続けると、体調不良や事故のリスクが高まります。
一方で、適度な負担であれば、収入ややりがいを保ちながら働き続けることも可能です。
ここでは、夜勤を続けるかやめるかを見極める3つの基準を紹介します。
体調と通院の記録を3か月分見直す
まず行うべきは、過去3か月間の体調変化を振り返ることです。
体調を点でなく「期間」で見ることで、疲労が慢性化していないか判断しやすくなります。
次のような記録を残しておくと効果的です。
- 睡眠時間と起床時の体調(5段階評価など)
- 通院・服薬の頻度
- めまい・動悸・頭痛などの症状
これらを週ごとにまとめると、変化が視覚的にわかります。
体調不良が増えている場合は、夜勤の回数を減らすか、シフトの変更を相談するタイミングです。
シフトと業務量を数字で比べる
次に、夜勤の頻度や業務量を具体的な数字で確認します。
「以前よりきつくなった」と感じるだけでなく、客観的に把握することで判断しやすくなります。
比較のポイントは以下の3点です。
- 1か月あたりの夜勤回数(例:5回→8回など)
- 1勤務あたりの平均歩数や移乗回数
- 勤務後の睡眠時間と疲労の残り具合
数値で可視化すると、どの要素が負担になっているのかが明確になります。
回数や作業量の増加が原因であれば、シフト調整や業務分担で改善できる可能性があります。
夜勤なしや軽い仕事への担当変更を相談する
体力面で限界を感じた場合は、夜勤そのものを見直す判断も必要です。
「辞める」だけが選択肢ではなく、「担当変更」や「勤務形態の調整」で続ける方法もあります。
具体的には以下のような選択肢があります。
- 夜勤なしのデイサービスや通所介護に異動
- 入浴介助や記録業務など、体の負担が軽い担当に変更
- 週2〜3日のパート勤務に切り替える
相談の際は「どの作業で疲れが出るか」「どの頻度なら続けられるか」を具体的に伝えると、理解を得やすくなります。
夜勤を続けるかどうかは、体力や生活リズム、家庭環境などによって異なります。

数字と記録をもとに冷静に判断することで、後悔のない選択ができますよ!
「このままでいいのかな…」と感じたら、介護士転職サイトへの相談がおすすめ
職場の人間関係や体力面、将来の働き方に不安を感じたときは、ひとりで抱え込まずに介護士転職サイトへ相談してみましょう。
- 応募前に職場の雰囲気や業務内容を詳しく知れる
- 面接対策や条件交渉までプロのアドバイザーがサポート
- ハローワークやネット上にはない非公開求人を紹介してもらえる
介護の職場は、同じ施設形態でも運営方針や人間関係によって働きやすさが大きく変わります。
そのため、最新の求人情報や内部事情に詳しい転職サイトを活用することが、後悔のない転職を実現する近道です。
登録はかんたん60秒!
最低2社は登録をして失敗のない
転職活動にしましょう
 | \介護職口コミNo.1/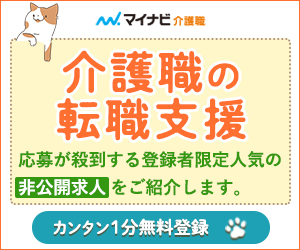 |
 | \残業なし求人多数/ |
 | \無資格・未経験OK/ |
介護士に本当に選ばれてる転職サイトTOP3
マイナビ介護職では、口コミ情報に精通していることに加えてブラックな職場は紹介しないという方針を徹底しています。
「◯◯老人ホームは介護士同士の派閥があって…」など、普通では聞けないような話も聞けるので、入ってからのミスマッチも事前に防ぐことが出来ます!

少しでも今の職場に迷いを感じたら、気軽に情報を集めてみてくださいね。
行動することで、次の選択肢がきっと見えてきますよ!